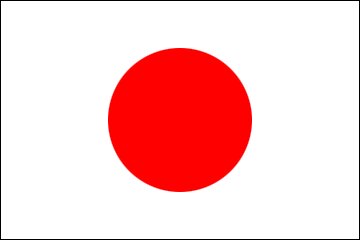REGA本部訪問(9月16日)
令和3年9月16日
緊急時にヘリコプターで遭難者や病人の救助に当たるrega(レガ)の活躍を御存知の方も多いかと思います。先日、チューリッヒ空港の一角にある本部にお邪魔しました。
日本版の<ドクター・ヘリ>のモデルでもあるレガは、ドイツ語のSchweizerische Rettungsflugwachtとフランス語のGarde aérienne suisse de sauvetageの名前のうち、最初の言葉をつなぎ合わせたもの(rega)だそうです。日本語に訳すと、<スイス航空救助隊>ということでしょうか。
スイスではハイキングに出かける機会が多いと思います。万一の事故の際、ハイカーが頼りにするのがレガの救難ヘリです。
「一報があれば、15分以内に現場に到着できるように、スイス国内のあちこちにヘリコプターを常駐させています。もちろん、24時間365日出動態勢です。隊員たちは、寝る時も靴を履いていつでも飛び出せるようにしています。連絡があれば5分で飛び出せます」と、理事長のHobmeier(ホプマイヤー)さんは胸を張りました。
ホプマイヤーさんは、大の日本好き。私が訪問してレガの説明を受けた際、冒頭のあいさつを日本語でしてくれました。現在、日本語の勉強中だそうで、日本語の先生の指導を受けながらあいさつ文を作り、それを日本語で読むべく、事前に練習されたのでしょう、なかなか上手でした。
日本にも出かけられているとのこと。上着の胸には、漢字で<火消>としるしたバッジが付けてありました。現代の救急隊員は、まさに江戸時代の「火消し」ですから当然ですね。日本への思い入れは尋常ではないと見受けました。
レガは、民間の非営利団体として運営されています。1952年に設立され、主に山岳地帯での遭難者救助に当たりますが、山岳地帯以外でも人の生死にかかわる緊急時に出動するそうです。
驚いたのは、スイス国内だけではなく全世界でスイス国民の救助活動に当たっていることです。その場合はヘリコプターではなく足の長いジェット機で救出作戦に当たります。小型機ながら医師、看護師が同乗し、必要な医療機器、ベッドもあります。必要なら家族も同伴できるようです。
ちょうど、私が菅谷書記官とレガ本部を訪問していた時、ジェット機は東京にいて、翌日、スイスに戻ってくる予定だと言っていました。たまたまパラリンピックに参加していたスイス人選手が急病で倒れ、現地での応急手当後、スイスに搬送するため日本に飛んだというのです。途中、一度給油に立ち寄るだけでスイスに直帰するとの説明でした。
そんな話を聞いていたその時、別の救急ジェットがチューリッヒ空港に着陸し、私たちがいる格納庫に入ってきました。着陸から格納庫までたった5分。外には救急車が待機しています。このジェットは、日本ではなくイタリアから病気のスイス人を載せてきた別便でした。約1時間半のフライトで患者を搬送できたそうです。
レガは非営利の民間機関だと書きましたが、運営資金はパトロンと呼ばれる資金提供者、つまりは会員の会費で成り立っています。スイス(リヒテンシュタインを含む)国民のほぼ半数がパトロンとして登録しているそうです。私も妻とともにパトロンになりました。
40スイスフラン(一人)払えば緊急時に助けてもらえますが、無料ではありません。後日、その費用が請求されますが、パトロンであれば結果的に負担が軽くなります。
ひと月ほど前、ベルン郊外にハイキングに出かけた折、頭上にレガのヘリが飛んでいました。しばらく旋回し、湖の岸辺に降りて待機した後、飛び去って行きました。肉眼で識別できる距離ではなかったので、どんな救助作戦だったのかわかりませんが、手際の良さに驚き、頼もしく感じた次第です。
レガは、人間だけでなく牛などの家畜も救助するそうです。山の牧草地でケガをしたり、あるいは不幸にして死んでしまったりした牛を運ぶこともあるようですが、「牛はただで運びます」とホプマイヤーさんは説明していました。理由は聞き漏らしたのですが、スイスでは牛が大事にされているんだなあ、と納得しました。
本部のビルの中にある指令室を拝見させてもらいました。3交代の24時間勤務で、オペレーターが待機しています。オペレーターは五か国語を使いこなして対応するそうです。多言語国家のスイスならでは、と感心しました。
前述したように、レガのサービスは山間僻地だけでなく、市街地も含め至る所が対象です。国境を越えて救出に向かうこともあります。万一に備えた保険として、年間40フランは決して高くはないように思いました。
日本版の<ドクター・ヘリ>のモデルでもあるレガは、ドイツ語のSchweizerische Rettungsflugwachtとフランス語のGarde aérienne suisse de sauvetageの名前のうち、最初の言葉をつなぎ合わせたもの(rega)だそうです。日本語に訳すと、<スイス航空救助隊>ということでしょうか。
スイスではハイキングに出かける機会が多いと思います。万一の事故の際、ハイカーが頼りにするのがレガの救難ヘリです。
「一報があれば、15分以内に現場に到着できるように、スイス国内のあちこちにヘリコプターを常駐させています。もちろん、24時間365日出動態勢です。隊員たちは、寝る時も靴を履いていつでも飛び出せるようにしています。連絡があれば5分で飛び出せます」と、理事長のHobmeier(ホプマイヤー)さんは胸を張りました。
ホプマイヤーさんは、大の日本好き。私が訪問してレガの説明を受けた際、冒頭のあいさつを日本語でしてくれました。現在、日本語の勉強中だそうで、日本語の先生の指導を受けながらあいさつ文を作り、それを日本語で読むべく、事前に練習されたのでしょう、なかなか上手でした。
日本にも出かけられているとのこと。上着の胸には、漢字で<火消>としるしたバッジが付けてありました。現代の救急隊員は、まさに江戸時代の「火消し」ですから当然ですね。日本への思い入れは尋常ではないと見受けました。
レガは、民間の非営利団体として運営されています。1952年に設立され、主に山岳地帯での遭難者救助に当たりますが、山岳地帯以外でも人の生死にかかわる緊急時に出動するそうです。
驚いたのは、スイス国内だけではなく全世界でスイス国民の救助活動に当たっていることです。その場合はヘリコプターではなく足の長いジェット機で救出作戦に当たります。小型機ながら医師、看護師が同乗し、必要な医療機器、ベッドもあります。必要なら家族も同伴できるようです。
ちょうど、私が菅谷書記官とレガ本部を訪問していた時、ジェット機は東京にいて、翌日、スイスに戻ってくる予定だと言っていました。たまたまパラリンピックに参加していたスイス人選手が急病で倒れ、現地での応急手当後、スイスに搬送するため日本に飛んだというのです。途中、一度給油に立ち寄るだけでスイスに直帰するとの説明でした。
そんな話を聞いていたその時、別の救急ジェットがチューリッヒ空港に着陸し、私たちがいる格納庫に入ってきました。着陸から格納庫までたった5分。外には救急車が待機しています。このジェットは、日本ではなくイタリアから病気のスイス人を載せてきた別便でした。約1時間半のフライトで患者を搬送できたそうです。
レガは非営利の民間機関だと書きましたが、運営資金はパトロンと呼ばれる資金提供者、つまりは会員の会費で成り立っています。スイス(リヒテンシュタインを含む)国民のほぼ半数がパトロンとして登録しているそうです。私も妻とともにパトロンになりました。
40スイスフラン(一人)払えば緊急時に助けてもらえますが、無料ではありません。後日、その費用が請求されますが、パトロンであれば結果的に負担が軽くなります。
ひと月ほど前、ベルン郊外にハイキングに出かけた折、頭上にレガのヘリが飛んでいました。しばらく旋回し、湖の岸辺に降りて待機した後、飛び去って行きました。肉眼で識別できる距離ではなかったので、どんな救助作戦だったのかわかりませんが、手際の良さに驚き、頼もしく感じた次第です。
レガは、人間だけでなく牛などの家畜も救助するそうです。山の牧草地でケガをしたり、あるいは不幸にして死んでしまったりした牛を運ぶこともあるようですが、「牛はただで運びます」とホプマイヤーさんは説明していました。理由は聞き漏らしたのですが、スイスでは牛が大事にされているんだなあ、と納得しました。
本部のビルの中にある指令室を拝見させてもらいました。3交代の24時間勤務で、オペレーターが待機しています。オペレーターは五か国語を使いこなして対応するそうです。多言語国家のスイスならでは、と感心しました。
前述したように、レガのサービスは山間僻地だけでなく、市街地も含め至る所が対象です。国境を越えて救出に向かうこともあります。万一に備えた保険として、年間40フランは決して高くはないように思いました。