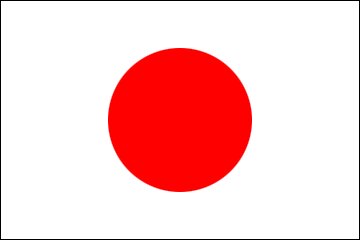白石大使の活動報告コメント:「新聞よ、再び立ち上がれ」
令和4年4月13日

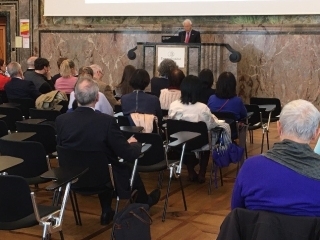
4月1日、チューリッヒ大学主催の「日本講演シリーズ」が始まり、そのオープニングを兼ねた第一回目の記念講演を同大学で行いました。
このシリーズは、知日派のケラハルス同大学欧州研究所長とシュワルツネッガー副学長が中心になって企画したものです。スイスで関心が高まっている日本を多角的に分析するため、多方面から日本人講師を招いて、大学の学生、関係者だけではなく一般市民にも開かれた講演会を重ねる予定です。
講演会場は大学の講堂です。ここは200人ほどを収容する大教室で、学外から要人が大学を訪れた際に記念講演の会場として利用されてきました。
実は、1946年9月、ヨーロッパでの戦争が終わったほぼ1年半後になりますが、当時、選挙に敗北して英国首相の座を退いていたウィンストン・チャーチルがこの講堂で記念講演をしています。
その際、チャーチルはヨーロッパが第2次世界大戦の悲劇から立ち直るためには、フランスとドイツの連携が不可欠だと指摘し、アメリカ合衆国にちなんで、両国を中心にした「ヨーロッパ合州国」を構築すべきだと強調しました。彼の提唱がEU(欧州連合)として実現したことを考えると、その先見性に脱帽せざるを得ません。
チューリッヒ大学での講演で、チャーチルは「今日はヨーロッパの悲劇について話したい」と語り始め、、「ヨーロッパよ、再び立ち上がれ」と結んでいます。
チャーチルが演説した1946年9月に、私は地球の反対側の日本で生まれました。偶然の一致ですが、チャーチルが立った演台を共有できる光栄に感謝しつつ、チャーチルの演説から冒頭部分を引用して話し始めることにしました。
日本の新聞界の現状と課題を紹介してほしいという大学側の要望で、「日本の新聞は、恐竜のように死に絶えてしまうのか」というタイトルにして、デジタル化の時代に紙の新聞は存続できるのか、の疑問に答えることにしました。30分ほどの講演です。
私は、チャーチルの演説を借りて、「今日はヨーロッパの悲劇ではなく、新聞の悲劇についてお話ししたい」と切り出しました。続けて現在、ヨーロッパで起きているウクライナの悲劇を取上げ、ロシアの侵略と残虐な戦争犯罪を非難しました。
その上で、戦争が起きた時、兵士だけでなく市民まで犠牲になるが、実は「真実」が戦争の最初の犠牲者になるのだと、アメリカの上院議員が第一次世界大戦時に指摘した言葉を紹介しました。
民主主義が成り立つには市民が自由に真実の情報に触れることができなければならず、それが為政者や政府の恣意的な検閲で妨げられれば民主主義は死んでしまいます。ロシアではまさに「真実」が犠牲者となり、独立系の新聞やテレビは戦争の実態を伝えることができません。政府系のメディアが政府に都合のいい情報だけを宣伝しています。これでは民主主義は存在できません。
アメリカ建国の父の一人、トーマス・ジェファーソンは「もし私が、新聞のない政府か、政府のない新聞か、いずれを選ぶかと尋ねられれば、ためらうことなく、後者を選ぶ」と明言しました。イギリスから独立を果たしたアメリカが、王様や貴族のいない共和国として存続するには民主主義が不可欠であり、その民主主義を定着させるには何より新聞がだいじなのだ、と言ったのです。
ロシアでは、ノーベル平和賞を受賞したジャーナリストが編集する反政府系の新聞が、ロシア政府の警告を受けて休刊を余儀なくされました。真実を伝え、政府を批判する表現の自由が圧殺されてしまいました。
こうした事例をスピーチの中で触れながら、新聞の重要性を強調しましたが、もちろん新聞だけが情報を伝える媒体(メディア)ではありません。新聞、雑誌あるいはテレビやラジオなど、古くからのいわゆるアナログ媒体だけでなく、新しく登場したインターネット、携帯電話などデジタル媒体が情報発信・伝達・拡散の面で大きな役割を果たすようになりました。
特に若い人たちの間では、新聞の代わりにスマホでニュースを読む、あるいはニュース映像や音声をテレビやラジオではなくスマホやパソコンで楽しむのが主流になっています。このため情報媒体としての新聞の存在感が薄まり、広告・宣伝媒体としての新聞の地位も下がり、新聞部数の減少や広告収入の減少に多くの新聞社が悩まされています。
この現象に立ち向かうため、新聞社も独自にデジタル・サービスを拡充し、ニュース以外の独自コンテンツもそろえて、新聞の付加サービス、あるいは独自の有料サービスとして展開し、新聞読者の引き留め、新規読者の獲得を目指すとともに、新聞部数や広告の減少分を補完する努力を続けています。
欧米の一部の新聞社は、新聞からデジタル・サービスへと重心を移すことによって苦境を乗り越えたといわれますが、楽観を許さない状況が続いているように思います。アメリカではいくつかの地方紙が経営難で姿を消し、欧州でも廃刊、休刊に追い込まれたり、新聞記者の削減を余儀なくされたりした新聞社が少なくありません。政府からの補助金でかろうじて生き延びている例もあります。
デジタル化の流れを押しとどめることはできませんが、デジタルの奔流の中で、信頼される情報媒体としての新聞を存続させるにはどうするか。恐竜のように環境の変化に適応できずに絶滅することを防ぐには、どのように対応していくのか。これがまさに現在の新聞に問われていることです。
紙の新聞の発行にとどまらず、新聞のコンテンツを生かしたデジタル・サービスを新聞購読者へのサービスとして提供したり、あるいは有料サービスとして展開したりしています。一方で、日本の新聞社は系列のテレビ会社を持ち、他にもいろいろ多角的に事業を行うことによって、新聞発行との相乗効果を上げながら経営基盤の強化に取り組んできました。今後もそうした努力を続けなければなりません。
紙の新聞とデジタル・サービス強化という混合型のビジネスで苦境を乗り越えようとしているわけで、これが維持できれば新聞が恐竜のように絶滅することはない、というのが私の結論です。
新聞記者が直接、見聞きした情報を記事にし、それを編集者が読んでニュース価値を判断した上で読者に届ける新聞は、フェークニュースが横行するネット社会の中で、信頼できる情報源として読者を導くナビゲーション機能を果たしています。航海に不可欠な羅針盤の役割です。
新聞社のデジタル・サイトは新聞記事のコンテンツを再編集したもので、根っこは新聞記者が集めた情報です。ジャーナリストの知識、経験、判断、表現力が凝縮された結果なのです。
こうしたことを盛り込んで私のスピーチを終えました。締めくくりに、ウクライナ情勢に触れ、日本が欧米諸国と連帯してウクライナを支援し、ロシアへの制裁に参加していること、北方領土問題を抱える日本にとってウクライナ戦争が対岸の火事ではないこと、アジアへの影響を注視していることなどを説明しました。
スイスの人たちに日本の立場を知ってもらう貴重な機会になったと思います。(4月12日記)
このシリーズは、知日派のケラハルス同大学欧州研究所長とシュワルツネッガー副学長が中心になって企画したものです。スイスで関心が高まっている日本を多角的に分析するため、多方面から日本人講師を招いて、大学の学生、関係者だけではなく一般市民にも開かれた講演会を重ねる予定です。
講演会場は大学の講堂です。ここは200人ほどを収容する大教室で、学外から要人が大学を訪れた際に記念講演の会場として利用されてきました。
実は、1946年9月、ヨーロッパでの戦争が終わったほぼ1年半後になりますが、当時、選挙に敗北して英国首相の座を退いていたウィンストン・チャーチルがこの講堂で記念講演をしています。
その際、チャーチルはヨーロッパが第2次世界大戦の悲劇から立ち直るためには、フランスとドイツの連携が不可欠だと指摘し、アメリカ合衆国にちなんで、両国を中心にした「ヨーロッパ合州国」を構築すべきだと強調しました。彼の提唱がEU(欧州連合)として実現したことを考えると、その先見性に脱帽せざるを得ません。
チューリッヒ大学での講演で、チャーチルは「今日はヨーロッパの悲劇について話したい」と語り始め、、「ヨーロッパよ、再び立ち上がれ」と結んでいます。
チャーチルが演説した1946年9月に、私は地球の反対側の日本で生まれました。偶然の一致ですが、チャーチルが立った演台を共有できる光栄に感謝しつつ、チャーチルの演説から冒頭部分を引用して話し始めることにしました。
日本の新聞界の現状と課題を紹介してほしいという大学側の要望で、「日本の新聞は、恐竜のように死に絶えてしまうのか」というタイトルにして、デジタル化の時代に紙の新聞は存続できるのか、の疑問に答えることにしました。30分ほどの講演です。
私は、チャーチルの演説を借りて、「今日はヨーロッパの悲劇ではなく、新聞の悲劇についてお話ししたい」と切り出しました。続けて現在、ヨーロッパで起きているウクライナの悲劇を取上げ、ロシアの侵略と残虐な戦争犯罪を非難しました。
その上で、戦争が起きた時、兵士だけでなく市民まで犠牲になるが、実は「真実」が戦争の最初の犠牲者になるのだと、アメリカの上院議員が第一次世界大戦時に指摘した言葉を紹介しました。
民主主義が成り立つには市民が自由に真実の情報に触れることができなければならず、それが為政者や政府の恣意的な検閲で妨げられれば民主主義は死んでしまいます。ロシアではまさに「真実」が犠牲者となり、独立系の新聞やテレビは戦争の実態を伝えることができません。政府系のメディアが政府に都合のいい情報だけを宣伝しています。これでは民主主義は存在できません。
アメリカ建国の父の一人、トーマス・ジェファーソンは「もし私が、新聞のない政府か、政府のない新聞か、いずれを選ぶかと尋ねられれば、ためらうことなく、後者を選ぶ」と明言しました。イギリスから独立を果たしたアメリカが、王様や貴族のいない共和国として存続するには民主主義が不可欠であり、その民主主義を定着させるには何より新聞がだいじなのだ、と言ったのです。
ロシアでは、ノーベル平和賞を受賞したジャーナリストが編集する反政府系の新聞が、ロシア政府の警告を受けて休刊を余儀なくされました。真実を伝え、政府を批判する表現の自由が圧殺されてしまいました。
こうした事例をスピーチの中で触れながら、新聞の重要性を強調しましたが、もちろん新聞だけが情報を伝える媒体(メディア)ではありません。新聞、雑誌あるいはテレビやラジオなど、古くからのいわゆるアナログ媒体だけでなく、新しく登場したインターネット、携帯電話などデジタル媒体が情報発信・伝達・拡散の面で大きな役割を果たすようになりました。
特に若い人たちの間では、新聞の代わりにスマホでニュースを読む、あるいはニュース映像や音声をテレビやラジオではなくスマホやパソコンで楽しむのが主流になっています。このため情報媒体としての新聞の存在感が薄まり、広告・宣伝媒体としての新聞の地位も下がり、新聞部数の減少や広告収入の減少に多くの新聞社が悩まされています。
この現象に立ち向かうため、新聞社も独自にデジタル・サービスを拡充し、ニュース以外の独自コンテンツもそろえて、新聞の付加サービス、あるいは独自の有料サービスとして展開し、新聞読者の引き留め、新規読者の獲得を目指すとともに、新聞部数や広告の減少分を補完する努力を続けています。
欧米の一部の新聞社は、新聞からデジタル・サービスへと重心を移すことによって苦境を乗り越えたといわれますが、楽観を許さない状況が続いているように思います。アメリカではいくつかの地方紙が経営難で姿を消し、欧州でも廃刊、休刊に追い込まれたり、新聞記者の削減を余儀なくされたりした新聞社が少なくありません。政府からの補助金でかろうじて生き延びている例もあります。
デジタル化の流れを押しとどめることはできませんが、デジタルの奔流の中で、信頼される情報媒体としての新聞を存続させるにはどうするか。恐竜のように環境の変化に適応できずに絶滅することを防ぐには、どのように対応していくのか。これがまさに現在の新聞に問われていることです。
紙の新聞の発行にとどまらず、新聞のコンテンツを生かしたデジタル・サービスを新聞購読者へのサービスとして提供したり、あるいは有料サービスとして展開したりしています。一方で、日本の新聞社は系列のテレビ会社を持ち、他にもいろいろ多角的に事業を行うことによって、新聞発行との相乗効果を上げながら経営基盤の強化に取り組んできました。今後もそうした努力を続けなければなりません。
紙の新聞とデジタル・サービス強化という混合型のビジネスで苦境を乗り越えようとしているわけで、これが維持できれば新聞が恐竜のように絶滅することはない、というのが私の結論です。
新聞記者が直接、見聞きした情報を記事にし、それを編集者が読んでニュース価値を判断した上で読者に届ける新聞は、フェークニュースが横行するネット社会の中で、信頼できる情報源として読者を導くナビゲーション機能を果たしています。航海に不可欠な羅針盤の役割です。
新聞社のデジタル・サイトは新聞記事のコンテンツを再編集したもので、根っこは新聞記者が集めた情報です。ジャーナリストの知識、経験、判断、表現力が凝縮された結果なのです。
こうしたことを盛り込んで私のスピーチを終えました。締めくくりに、ウクライナ情勢に触れ、日本が欧米諸国と連帯してウクライナを支援し、ロシアへの制裁に参加していること、北方領土問題を抱える日本にとってウクライナ戦争が対岸の火事ではないこと、アジアへの影響を注視していることなどを説明しました。
スイスの人たちに日本の立場を知ってもらう貴重な機会になったと思います。(4月12日記)