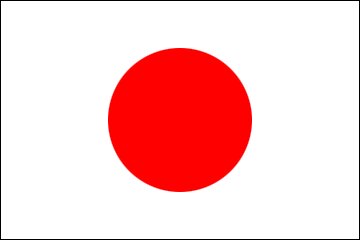白石大使の活動報告コメント:「不思議な国・日本、その魅力」
令和4年4月14日

4つの異なる言語が公用語であるスイスには、それぞれを母語として育った地域の人の集まりがあるようです。ドイツ語圏のベルンでもそうしたグループがあり、その一つであるフランス語を母語とする人たちの会「ベルン・アキュイー(ベルンのおもてなし、という意味でしょうか)」に招かれ、スピーチをすることになりました。
発端は、昨年の駐スイス・フィンランド大使の送別会に出席した際、懇談の席で同会幹部の女性から、「機会があればスピーチをしていただきたい」というお誘いを受けたことです。それが、つい先日、ベルン旧市街にある建物の一室で実現しました。
スピーチの題材は御自由に、ということでしたが、今年の2月頃から準備を始めました。今回の講演とは別に、その直前にチューリッヒ大学での講演が予定されていたため、二つのスピーチの草稿作りを同時期に並行して進めることになりました。
「ベルン・アキュイー」は英語のスピーチをフランス語に通訳します、ということでしたが、通訳の手間と時間を省くため、初めてフランス語でのスピーチに挑戦しました。フランス語圏のジュネーブで日本人会新年会が開かれた際、簡単な挨拶をフランス語でやった経験はあるのですが、30分ほどのスピーチをフランス語でするのは初めての挑戦です。
フランス語のスピーチは私の秘書がフランス語圏の出身なので、彼女に翻訳を頼むことにしました。彼女は日本語も堪能なのですが、日本語から翻訳するより英語からの方がやりやすい、というので結局、チューリッヒ大学での講演(これはもともと英語で30分程度、という要望)とこちらのスピーチを、それぞれ異なるテーマで英語草稿にして用意する事態になったわけです。
「ベルン・アキュイー」の方は、今年2月と3月に当館の広報文化センターで上映した2本の映画からヒントを得て、日本人の好きな和食と温泉をテーマに日本の魅力を伝えたいと考えました。
和食は「武士の献立」という映画がトピックです。江戸時代の加賀藩(現在の石川県)で、大名に仕える料理を専門とする武士とその妻が、近隣の大名を招いて藩主が開く饗宴料理を準備するため奮闘する姿を描いた作品です。
二人で藩内をくまなく歩き回り、海や山、畑や田んぼから集めた多彩な素材を、いろいろの調理法で色、香り、姿、かみ応えに変化をつけながら、配下の「料理侍」を指揮してみごとに並べていきます。映画を見ながら何度もつばを飲み込みました。
温泉は、ヤマザキ・マリさん原作の漫画を映画化した「テルマエ・ロマエ」です。ローマ時代の温泉建築技師ルシウスが、当時のハドリアヌス皇帝から戦争で傷ついた兵士をいやす温泉をつくるようにと命じられます。ルシウスはローマ市内の温泉につかりながら思案するのですが、名案が浮かびません。
そんなとき、何かの拍子で浴槽の中に沈み込むと、それがタイム・トンネルの入り口になっていて、温泉の地下トンネルを通り、現代の東京にある銭湯の湯船へと、タイム・スリップして突然浮上します。そこで彼は、現代の日本人、ルシウスの表現を借りると「平たい顔」の部族が温泉造りの優れた技術と知恵を持っていることを知ります。
数日後、ルシウスは再び突然、温泉トンネルに落ちてローマの温泉に逆戻りします。そして日本で学んだ温泉造りの知恵と技術を生かし、ユニークな温泉を皇帝のためにつくり高い評価を得る、という話になります。
この2本の映画を導入にして、スピーチをつないでいきました。日本の食文化や習俗に限らず、日本とスイスの長い間の交流が相互に影響を与え、お互いの理解を深めていることを指摘しました。それが昨年の東京オリンピックで更に拍車がかかったように思います。
東洋と西洋がお互いに触発しながら新しい価値や美を創造してきたこと、情報通信技術の発達であっという間に時空を超えて文化が広がること、世界の若者に人気のある日本のアニメが、平安時代の源氏物語絵巻や鳥獣人物戯画に遡る歴史を持つことなど、私の個人的な見解を交えて説明しました。
たどたどしいフランス語でどれだけ理解してもらえたのか、疑問ですが、スピーチ後の質疑応答では日本の教育制度、定年と年金支給の開始年齢、人気のスポーツなど多岐にわたる質問が続いて、これは英語でやりとりをさせてもらいましたが、参加者の日本に対する関心の高さを痛感しました。
機会があれば、またこうした日本文化紹介を積極的に行っていきたいと思っています。(4月12日記)
発端は、昨年の駐スイス・フィンランド大使の送別会に出席した際、懇談の席で同会幹部の女性から、「機会があればスピーチをしていただきたい」というお誘いを受けたことです。それが、つい先日、ベルン旧市街にある建物の一室で実現しました。
スピーチの題材は御自由に、ということでしたが、今年の2月頃から準備を始めました。今回の講演とは別に、その直前にチューリッヒ大学での講演が予定されていたため、二つのスピーチの草稿作りを同時期に並行して進めることになりました。
「ベルン・アキュイー」は英語のスピーチをフランス語に通訳します、ということでしたが、通訳の手間と時間を省くため、初めてフランス語でのスピーチに挑戦しました。フランス語圏のジュネーブで日本人会新年会が開かれた際、簡単な挨拶をフランス語でやった経験はあるのですが、30分ほどのスピーチをフランス語でするのは初めての挑戦です。
フランス語のスピーチは私の秘書がフランス語圏の出身なので、彼女に翻訳を頼むことにしました。彼女は日本語も堪能なのですが、日本語から翻訳するより英語からの方がやりやすい、というので結局、チューリッヒ大学での講演(これはもともと英語で30分程度、という要望)とこちらのスピーチを、それぞれ異なるテーマで英語草稿にして用意する事態になったわけです。
「ベルン・アキュイー」の方は、今年2月と3月に当館の広報文化センターで上映した2本の映画からヒントを得て、日本人の好きな和食と温泉をテーマに日本の魅力を伝えたいと考えました。
和食は「武士の献立」という映画がトピックです。江戸時代の加賀藩(現在の石川県)で、大名に仕える料理を専門とする武士とその妻が、近隣の大名を招いて藩主が開く饗宴料理を準備するため奮闘する姿を描いた作品です。
二人で藩内をくまなく歩き回り、海や山、畑や田んぼから集めた多彩な素材を、いろいろの調理法で色、香り、姿、かみ応えに変化をつけながら、配下の「料理侍」を指揮してみごとに並べていきます。映画を見ながら何度もつばを飲み込みました。
温泉は、ヤマザキ・マリさん原作の漫画を映画化した「テルマエ・ロマエ」です。ローマ時代の温泉建築技師ルシウスが、当時のハドリアヌス皇帝から戦争で傷ついた兵士をいやす温泉をつくるようにと命じられます。ルシウスはローマ市内の温泉につかりながら思案するのですが、名案が浮かびません。
そんなとき、何かの拍子で浴槽の中に沈み込むと、それがタイム・トンネルの入り口になっていて、温泉の地下トンネルを通り、現代の東京にある銭湯の湯船へと、タイム・スリップして突然浮上します。そこで彼は、現代の日本人、ルシウスの表現を借りると「平たい顔」の部族が温泉造りの優れた技術と知恵を持っていることを知ります。
数日後、ルシウスは再び突然、温泉トンネルに落ちてローマの温泉に逆戻りします。そして日本で学んだ温泉造りの知恵と技術を生かし、ユニークな温泉を皇帝のためにつくり高い評価を得る、という話になります。
この2本の映画を導入にして、スピーチをつないでいきました。日本の食文化や習俗に限らず、日本とスイスの長い間の交流が相互に影響を与え、お互いの理解を深めていることを指摘しました。それが昨年の東京オリンピックで更に拍車がかかったように思います。
東洋と西洋がお互いに触発しながら新しい価値や美を創造してきたこと、情報通信技術の発達であっという間に時空を超えて文化が広がること、世界の若者に人気のある日本のアニメが、平安時代の源氏物語絵巻や鳥獣人物戯画に遡る歴史を持つことなど、私の個人的な見解を交えて説明しました。
たどたどしいフランス語でどれだけ理解してもらえたのか、疑問ですが、スピーチ後の質疑応答では日本の教育制度、定年と年金支給の開始年齢、人気のスポーツなど多岐にわたる質問が続いて、これは英語でやりとりをさせてもらいましたが、参加者の日本に対する関心の高さを痛感しました。
機会があれば、またこうした日本文化紹介を積極的に行っていきたいと思っています。(4月12日記)