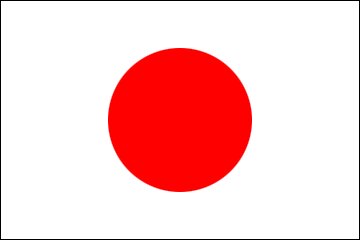白石大使の活動報告コメント「スイスでの手習い」
令和3年11月1日

10月8日、大使館の多目的ホールで書道ワークショップが開かれ、飛び込みで参加させてもらいました。ワークショップと言えば、研修会、研究会の意味ですが、スイスの人々に書道を体験してもらおう、という試みです。
午前と午後の二部制で行われ、午前の部は高校生22人、午後の部は日本文化に関心を持つ大人を対象に26人が参加しました。(書道ワークショップの模様はこちら[日本文化体験講習会(Japan aktiv erleben)の一環として、書道ワークショップを開催しました]をご覧ください。)
会場には二人がけのテーブルが並び、毛筆と墨汁の入った硯、習字用の半紙が準備されています。最初に講師のスルツベルゲル=三木佐和子さんが、中国における漢字の誕生、日本への伝来、漢字から平かな、カタカナが誕生した歴史を簡単に説明。
それを踏まえて、アルファベットと異なり、漢字は基本的に右から左へ書き進め、筆順は上から下が原則などと易しく解説しました。
基礎的学習が済んだ後、ワークショップの生徒さんたちが実際に筆を執り、まずはカタカナで自分の名前を書きます。お手本はテーブルに置かれた名札にカタカナで印刷されています。
それを終えると、花、愛、幸福などと書かれた手本から好みの文字を一つ選んで漢字を書きます。三木先生が会場を回り、生徒さんの筆の持ち方を直したり、書き順を教えたりしながら手ほどきをしていました。
私も末席に座って久しぶりに筆を持ちました。近くのテーブルで高校生、あるいは大人の人が初めての書道に取り組んでいる姿を見て、小学生時代の習字の時間を思い出しました。互いに見せ合いながら楽しんでいる子供たちの作品に、先生が朱墨で筆を入れていた姿が印象に残っています。
大使になる前、新聞社の社長を務めていた際、毛筆で署名を求められる機会が時々あるぞ、と先輩から聞いていたので、書道の先生にお願いして月1回ほど個人指導を受けていました。2年ほど続けたのですが、それも時間の余裕がなくなり途中で終わってしまいました。
時々、記帳の機会があり、小筆と墨が用意されていた時は
金釘流ながら筆で挑戦しました。肩書と名前だけですが緊張したものです。大使の署名は原則、漢字を使い、万年筆型の筆ペンでしのいでいます。
そんな経緯もあり、大使館主催のワークショップに顔を出した次第です。スイスの人々にとっては書道のワークショップは初体験だったと思いますが、筆の持ち方、上下左右の運筆に戸惑いながら、真剣な表情で筆を動かしていました。
書道ワークショップは大使館に付属する広報文化センターが企画したものです。主宰した菅谷書記官は「書道は日本の伝統文化の一つです。書道を通してスイスの人々に日本文化への理解を深めてもらおうと企画しました。短時間のワークショップでしたが、参加者に楽しんでもらえたと思います」と述べています。
小生にとっても貴重な経験になりました。日本から書道の練習道具を持ってきていたのでそれを初めて使いました。意外なところで役に立った次第です。
午前と午後の二部制で行われ、午前の部は高校生22人、午後の部は日本文化に関心を持つ大人を対象に26人が参加しました。(書道ワークショップの模様はこちら[日本文化体験講習会(Japan aktiv erleben)の一環として、書道ワークショップを開催しました]をご覧ください。)
会場には二人がけのテーブルが並び、毛筆と墨汁の入った硯、習字用の半紙が準備されています。最初に講師のスルツベルゲル=三木佐和子さんが、中国における漢字の誕生、日本への伝来、漢字から平かな、カタカナが誕生した歴史を簡単に説明。
それを踏まえて、アルファベットと異なり、漢字は基本的に右から左へ書き進め、筆順は上から下が原則などと易しく解説しました。
基礎的学習が済んだ後、ワークショップの生徒さんたちが実際に筆を執り、まずはカタカナで自分の名前を書きます。お手本はテーブルに置かれた名札にカタカナで印刷されています。
それを終えると、花、愛、幸福などと書かれた手本から好みの文字を一つ選んで漢字を書きます。三木先生が会場を回り、生徒さんの筆の持ち方を直したり、書き順を教えたりしながら手ほどきをしていました。
私も末席に座って久しぶりに筆を持ちました。近くのテーブルで高校生、あるいは大人の人が初めての書道に取り組んでいる姿を見て、小学生時代の習字の時間を思い出しました。互いに見せ合いながら楽しんでいる子供たちの作品に、先生が朱墨で筆を入れていた姿が印象に残っています。
大使になる前、新聞社の社長を務めていた際、毛筆で署名を求められる機会が時々あるぞ、と先輩から聞いていたので、書道の先生にお願いして月1回ほど個人指導を受けていました。2年ほど続けたのですが、それも時間の余裕がなくなり途中で終わってしまいました。
時々、記帳の機会があり、小筆と墨が用意されていた時は
金釘流ながら筆で挑戦しました。肩書と名前だけですが緊張したものです。大使の署名は原則、漢字を使い、万年筆型の筆ペンでしのいでいます。
そんな経緯もあり、大使館主催のワークショップに顔を出した次第です。スイスの人々にとっては書道のワークショップは初体験だったと思いますが、筆の持ち方、上下左右の運筆に戸惑いながら、真剣な表情で筆を動かしていました。
書道ワークショップは大使館に付属する広報文化センターが企画したものです。主宰した菅谷書記官は「書道は日本の伝統文化の一つです。書道を通してスイスの人々に日本文化への理解を深めてもらおうと企画しました。短時間のワークショップでしたが、参加者に楽しんでもらえたと思います」と述べています。
小生にとっても貴重な経験になりました。日本から書道の練習道具を持ってきていたのでそれを初めて使いました。意外なところで役に立った次第です。