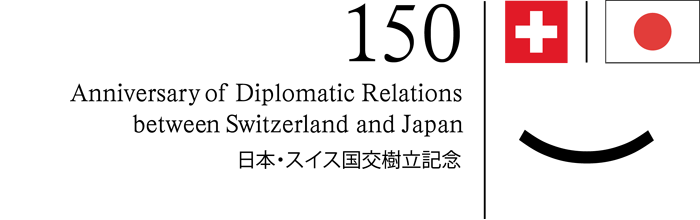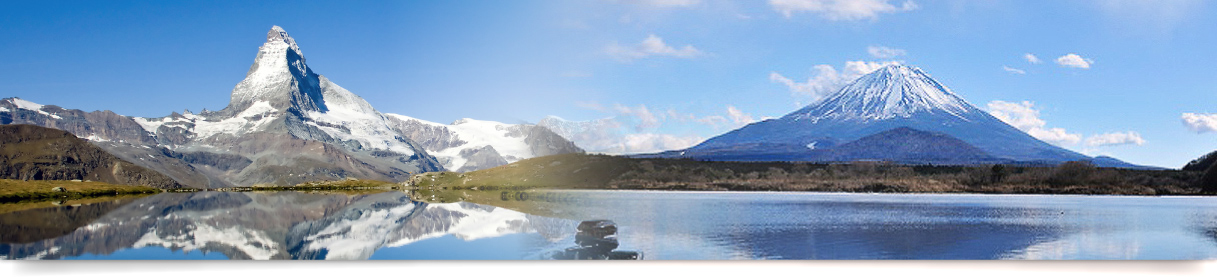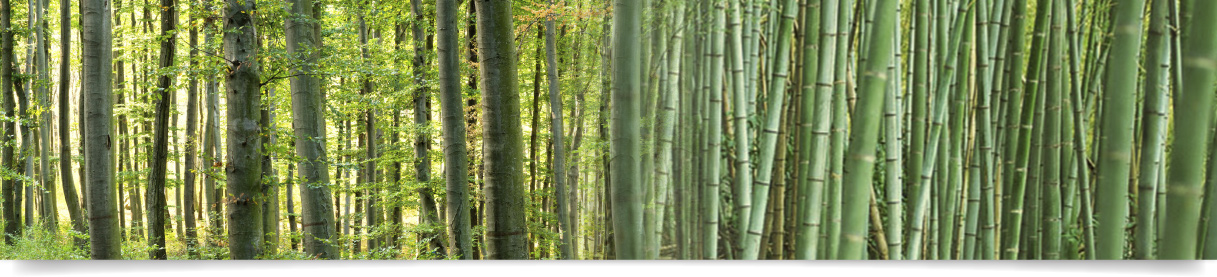「日本とスイスの150年-そして?」
日本とスイスの二国間関係は、1864年2月6日、第14代将軍徳川家茂(1846~66)とスイス連邦との間で最初の修好通商条約が締結されたことにより確立されました。当時の日本の暦でいえば、文久3年12月29日のことでした。これが現在、日本とスイスが2014年に国交樹立150周年を祝うための準備を進めている理由です。
ではいったい、スイスというヨーロッパの真ん中に位置し、海軍も植民地ももたない内陸国が、どのような考えをもって、首都ベルンから9,674キロも東方に離れ、鎖国を長く続けていた日本という国と、経済的・外交的な関係を築こうとしたのでしょうか?
実は、日本とスイスは複数の共通点を持っています。国土の一部でしか農業が出来ない急峻で山がちな地形、わずかな天然資源と勤勉な国民。スイスでは日本に比べて地震の脅威は低いものの、両国は、厳しく、時には残酷な自然の力を受け入れ、畏敬の念を抱いてきました。
スイスにとって最後の内戦となった1847年の「分離同盟戦争」終結後、スイスは1848年に新憲法を制定し、産業革命と活発な経済成長の新しい時代に入りました。特に、スイスの時計産業は、新たな市場を求めました。
当時の日本は、江戸時代(1603~1868)が終焉を迎えようとしていた時期で混乱が見られました。江戸幕府は、開国を拒む朝廷、幕府を倒して新政権を望む尊王攘夷派の革新的勢力と対峙する一方、開国を強硬に求める外国の列強からの圧力にもさらされていました。1853年にペリー提督と彼の艦隊が浦賀湾に到着し、1858年に最初の修好通商条約を日米間で結ぶと、幕府は続けてオランダ、ロシア、英国、フランスと同様の条約に署名しました。
スイスの産業界は、こうした状況を知って、既に1859年には連邦政府に日本への使節団を派遣することを要求しました。そこで派遣されたのが、ルドルフ・リンダウ(1829~1910)でした。しかし、彼は、日本が更なる条約交渉を行う準備ができたら、日本はスイスを優先的に扱うという約束を得ることしかできず、帰国の途につきました。
そこで、連邦内閣は、1862年の末に、エメ・アンベール(1819~1900)を特命全権公使に任命し、日本との条約交渉を進めるよう指示を出しました。1863年に日本に到着してからほぼ1年後、彼は、オランダの外交官ディルク・グラーフ・ファン・ポルスブルック公使の仲介もあって、1864年2月6日に条約を締結することができました。
この条約は、スイスにとって、多くの実りある経済活動の始まりを意味するものでした。武器、時計、精密機器などを日本に輸出し、高級な絹糸をスイスに輸入しました。ファーブル・ブラント、ジーベル・ヘグナー、リーバーマン・ヴェルチリなどの商社が横浜に、そして大阪・神戸に拠点を構え、成功を収めました。
1868年、江戸幕府が崩壊し、天皇を中心とした明治政府(1868~1912)へと時代が転換すると、日本では内戦の時期を経て、京都から江戸への首都移転と、江戸から東京への改称が行われました。
明治新政権の下、日本は、社会の欧米化につながる抜本的な改革を開始しました。よく「明治維新」という言葉が使われますが、実際には、日本社会の「革命」でした。日本政府が封建制度廃止や仏教と神道の分離などのためにとった措置は、スイスにまでも影響を及ぼしました。品川寺(ほんせんじ)の梵鐘は、その一例です。この鐘は持ち出されてスイスに輸出されましたが、これを入手したジュネーブ市が、1930年に品川寺に返還しました。これがきっかけとなり、品川区とジュネーブ市の友好が育まれ、1991年に正式に友好憲章が締結されたのです。これは、今日の両国を結ぶ、多くの特別な関係の一つに過ぎません。
オランダの東インド会社のおかげで、スイス製品は、既に江戸時代には日本に到達していましたが、ネスレ、チバ(製薬会社で現在はノバルティス社)など幾つかのスイスの製造業者は20世紀初頭になって初めて日本に拠点を置きました。
スイスに来た最初の日本人は、1867年に訪問した徳川昭武(1853~1919)の使節団であったと考えられます。その後、1870年~74年にジュネーブへ留学し、元帥になった大山巌(1842~1916)のような学生たちが続きました。この伝統は今日の大学院レベルでの奨学生交流プログラムに受け継がれています。明治の代になって、最初の公式な日本代表団である、有名な岩倉具視(1825~83)のミッションが、1870年6月、世界旅行の途上でスイスを訪問し、永世中立、創設直後の赤十字社、そしてスイスの民兵制度などに関心を寄せました。
その後19世紀末から20世紀にかけて、日本が国際社会で力を伸ばし、第二次世界大戦へと突入していく中でも、日本とスイスの関係が途絶えることはありませんでした。中立国スイスは第二次世界大戦中、日本における連合国の利益代表をしていました。
そして、1945年8月の原爆投下直後に広島入りしたマルセル•ジュノー医師(1904~61)と赤十字国際委員会の活躍は、両国関係の新たな幕開けを告げるものとなりました。
終戦直後のスイスからの投資やスイスの最新技術の導入は、日本の復興に貢献しました。市場の統合が徐々に進む中、両国間の貿易関係は、特に時計業界において相互補完関係と激しい競争との狭間で発展してきました。
スイスがヨーロッパの中心にありながらEUに加盟していないという特別な状況は、多くの日本企業がヨーロッパ本部をスイスに設置することを後押ししました。
日本とスイスは、両国とも輸出に強く依存し、自由貿易に関しては同じ価値観、農業や食糧自給に関しては同じ懸念を共有しています。
2009年に発効した両国間の新たな自由貿易協定は、両国が利益共同体であることを証明するものです。そして、この数十年間、両国間の科学技術交流も深化してきました。
スイスのアルプスの風景の美しさは、早くから日本からの観光客を集めており、スイスの山岳鉄道で見られる安全に関する注意書きは、多くの場合、日本語で書かれています。
ルツェルンにある木製のカペル橋の火事(1993年)が日本人の心を動かし、日本人が寛大にもその再建に参加したように、2011年3月11日の東日本大震災は、悲しい出来事でしたが、スイスにおいて日本に対する連帯の運動を引き起こし、両国国民の間の絆を更に強くするものとなりました。
国交樹立150周年というお祝いは、過去を振り返りながら、未来に目を向ける機会です。これを念頭に、スイスと日本は、この地球の平和と繁栄に貢献するためにどのような役割を果たすことができるのでしょうか。
フィリップA. F. ニーゼル