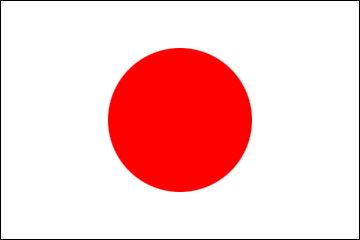安全の手引き
<目次>
1 はじめに
2 防犯の手引き
(1) 防犯の基本的心構え
(2) スイスにおける犯罪発生状況
(3) 防犯のための注意事項
(4) 交通事情と事故対策
(5) テロ対策
(6) 自然災害(防災)
(7) 緊急時の連絡先
3 在留邦人用緊急事態対処マニュアル
(1) 平素の準備と心構え
(2) 緊急時の行動
1 はじめに
海外における安全確保は、「自分の身は自分が守る」ことが大原則です。それでは、日頃どのような注意・努力を行えば安全を確保できるのでしょうか。
それには
(1) 海外で生活する上での心構えをしっかり持つこと
(2) 安全に関する情報を集め、それに基づき行動すること
(3) 緊急時のための連絡先を確認し、連絡手段を確保しておくこと
以上3点が安全確保のために大変重要です。
この手引きは、スイスに観光で訪れる方及び新たな生活を始める方を主な対象として、当地に滞在される方の安全対策のために、上記ポイントにそって作成しました。
この資料が、安全で快適な生活を送るための参考となれば幸いです。
(※在ジュネーブ領事事務所が管轄するジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州を訪問予定の方は、在ジュネーブ領事事務所のホームページもご参照ください)
2 防犯の手引き
(1) 防犯の基本的心構え
海外生活における安全対策の基本的心構えとして次のことが挙げられます。ア 自分と家族の安全は、自分自身で守る。
この心構えは、極めて重要です。スイスは比較的治安の良い国だと思われがちですが油断こそが大敵です。
イ 予防が最良の危機管理
予防こそが最高かつ最重要の危機管理です。
ウ 悲観的に準備し、楽天的に行動する
「備えあれば憂いなし」です。
エ 安全のための三原則の厳守
「目立たない」・「行動を予知されない」・「用心を怠らない」
オ 住宅の安全確保
住宅は生活の基盤です。その安全を確保することが安全対策の最優先事項です。
カ 現地社会に溶け込む
いざという時に助けが得られ、周囲からの情報を得やすくなります。
キ 精神衛生と健康管理の留意
環境、習慣等の違いから長期の緊張を余儀なくされる場合が多いので、精神面、肉体面の自己管理が重要です。
(2) スイスにおける犯罪発生状況
ア 警察組織
スイスは、連邦及び州にそれぞれ警察組織があります。これに加え、一部の市町村においては、別個に組織される独自の警察も存在します。 例えば、チューリッヒ州では、州内を管轄する「チューリッヒ州警察」に加え、チューリッヒ市、ウスター市等の主な自治体において「市警察」が組織されており、州警察との連携・協力を強化しています。イ 一般犯罪
(ア) スイスは、一般犯罪の発生率が日本に比べ高い状況です。発生率の高い州からチューリッヒ州、ベルン州、ヴォー州、ジュネーブ州バーゼル・シュタット準州となっています。特に、邦人旅行者が空港又は空港に接続する鉄道駅等で置き引きや窃盗被害に遭う事例が多発しています。(イ) 最近では、空港でのクレジットカード詐欺も発生しています
(ウ) 短期滞在(観光等)に限らず、在留邦人も十分な注意が必要です。
当国における安全対策情報は、当館領事メール及び当館ホームページで随時提供・更新しています。最新情報の入手に心掛けてください。
【2020年~2024年の主な犯罪別件数】
| 事件種別 | 2020年(件) | 2021年(件) | 2022年(件) | 2023年(件) | 2024年(件) | 前年比(%) |
| 殺人 | 47 | 42 | 42 | 53 | 45 | -15 |
| 殺人未遂 | 206 | 184 | 195 | 229 | 233 | 2 |
| 傷害(重度) | 669 | 650 | 762 | 880 | 1'029 | 17 |
| 傷害 | 7'444 | 6'639 | 7'516 | 7'440 | 7'347 | -1 |
| 窃盗 | 113'645 | 108'751 | 128'317 | 155'487 | 162'676 | 5 |
| 車両盗難 | 40'496 | 40'021 | 46'385 | 54'517 | 59'600 | 9 |
| 強盗 | 1'949 | 1'736 | 1'941 | 1'930 | 2'113 | 9 |
| 詐欺 | 19'338 | 22'597 | 24'195 | 29'314 | 34'392 | 17 |
| 恐喝 | 883 | 1'514 | 1'770 | 1'765 | 1'554 | -12 |
| 住居侵入 | 5'671 | 5'741 | 5'701 | 6'529 | 6'936 | 6 |
| 強姦 | 713 | 757 | 867 | 839 | 1'086 | 29 |
| 放火 | 893 | 779 | 843 | 771 | 679 | -12 |
| 認知総数 (その他含む) |
421'678 | 415'008 | 458'549 | 522'558 | 563'633 | 8 |
(3) 防犯のための注意事項
ア 空き巣・忍び込み・押し入り強盗
スイス国内で近年空き巣や忍び込みの件数が増加しています。アパート・一軒家を問わず、一般的にどの家も被害対象となり得ます。日頃から窓やドアの開閉には気をつけ、ほんの一瞬であっても安易に開放したままにしないよう気をつけてください。
その他、隣家(室)等との良好な関係を維持し相互に注意しあえる環境づくりも大切です。
(ア)住居の選定
事情をよく知る人から事前に情報を集めると共に、地域環境(居住地域の治安状況)や建物構造(住居の堅牢性)などの観点から安全性の高い住居を選定されることをお勧めします。さらに、必要に応じて補助錠や開閉チャイム、点灯タイマー等の設置を検討してください。
住居の選定には以下の点に注意してください。
居住地域の治安状況
(1) 付近に治安上問題となる場所はないか。
➢ 犯罪多発地域またはその付近ではないか。
➢ 麻薬や犯罪の巣窟となっているとされる公園や駅など危険地域(No-Go-Areas) に近接していないか。
➢ テロの標的となる恐れのある建物や場所(宗教関連施設、観光施設、ショッピングモールなど)の近くではないか。
(2) 通勤通学に利用する道路の安全性はどうか。
➢ 夜道が暗く、閑散としていないか。
➢ 経路上に、いざという時に逃げ込める施設(警察や病院、商店等など)があるか。
住居の安全性・堅牢性
(3) 玄関扉や窓の強度や防犯性能は十分か。
➢ ドアや窓が堅固であること(ドア本体、ドア枠、蝶番、錠、補強金具、錠の受け座は相互に調和しているか)。
➢ ドアスコープやドアチェーンがあるか。
➢ 玄関等室外の照明設備(センサー付照明等)が整っているか。
(4) 近隣住民がどのような人か確認。
➢ 緊急時には助け合える良好な関係が築けるか。
(5) 敷地内に居住者専用の駐車場・駐輪場があるか。
➢ 盗難や車上ねらいなどの被害防止のため、路上駐車はできる限り避ける。
(6) 家主・管理人の対応。
➢ いざというときにすぐに連絡が取れる家主や管理人がいる住居を選定することが望ましい。
(イ)空き巣、忍び込み、押し入り強盗対策
(1) 在宅中の対策
➢ 帰宅したら(部屋に入ったら)オートロックだけでなく、すぐに玄関を施錠する習慣をつける(オートロックは外側から簡単に開けることができます)。
➢ 予期せぬ来訪者が突然呼び鈴を押した場合、身元確認ができなければ、むやみに解錠しない(特にアパートの正面玄関)。
➢ 建物内の廊下、庭、地下駐車場に見かけぬ人物を見かけた時は、その人の動きや様子に注意を払い、不審な点があれば警察に通報する。
➢ 使用していない部屋(地下室を含む)の鍵は常にかけておく。
(2) 外出時の対策
➢ 窓、バルコニーやテラスのドアを、斜めに半開きにしたままで留守にしない(この場合、家財保険会社は窓などを開けたままの状態とみなし、 保険が適用されないこともあります)。
➢ 外出の際はたとえ数分であってもオートロックだけの状態や不注意に開けっ放しにせず、必ず鍵をかける(鍵は必ず最後まで廻してください)。
(3) 長期不在時の対策
➢ 郵便受けに新聞、ダイレクトメール、手紙などがたまらないようにする。(信頼できる隣人や友人に定期的に郵便受けを確認してもらう。)
➢ 点灯タイマーまたはセンサー付照明を取り付ける。
(4) その他、一般的な対策
➢ 地下物置に高価な家財を保管しない。
➢ 個々の品の写真、購入価格、購入日などを記した貴重品リストを作成しておく。
イ 外出時の各種犯罪対策
犯人は、予めターゲットを絞った上で、狙い定めた者の行動を監視し、犯行のチャンスを狙っています。外出時は「誰かに見られているかもしれない」といった意識を常に持ち、周囲を警戒するなどして犯人に隙を見せないようにしてください。(ア)スリ・置き引き
スリや置き引きは、空港、駅、公共の乗り物内、ホテル等で日常的に発生しています。用心していても一瞬の隙きをつかれ、注意をそらされた間に盗難に遭っています。
スリや置き引き被害に遭いやすい場所
➢ 不特定多数の人が行き交う人混みの中(主要ターミナル駅、空港、公共交通機関内(長距離列車、Sバーン、地下鉄、バス、トラム)、デパート、 スーパーマーケット、市場など)
➢ イベント会場(サッカーやマラソン等のスポーツイベント、見本市(メッセ)、 クリスマス・マーケットなど)
➢ ホテルやレストラン(チェックインカウンター、ロビー、朝食会場など)
スリや置き引きは、2~3人のグループで行われるケースが多く、彼らの手口は、おおよそ次の3段階で構成されています。
スリや置き引きの手口
(1)1人目が対象者(被害者)の気をそらすために、対象者の行く手を邪魔します。通常「ブロック係(Blocker)」と呼ばれる人です。
(2)2人目が対象者のカバンの中から財布を抜き取ります。通常「抜き取り係(Zieher)」と呼ばれる人です。
(3)犯行を他人の目から上手に隠してしまうのが3人目の「目隠し係(Abdecker)」です。
犯人グループには若い女性が加わっていることもあり、親切を装い、一目では犯罪者かどうか見分けがつかない場合が多いので注意が必要です。
この手口を応用した具体的犯行として次のような例があります。
●電車等、乗車時のお手伝いスリ
ブロック係は、人々がトラムや電車に乗る際、スーツケース等重量物の運搬を手伝うと申し出て最初に乗り込み、入口付近で停滞することにより人々の乗車を遅らせます。同時に、抜き取り係が、乗車のため並んでいる対象者(被害者)が入口付近で気を取られている隙に財布やカバンを盗む手口です。
●ぶつかりスリ
エスカレーターや混雑した駅のような人混みにいる時、犯人が故意に体を押しつけたり、ぶつかってきたりします。それに気を取られている隙に共犯者がカバンや財布を抜き取る手口です。
●押しのけスリ
混雑した駅のプラットホーム等で犯人が人を押しのけて不自然に対象者に寄って来ます。対象者が不快に思い背を向けた時にカバンから物を抜き取る手口です。
●ご案内スリ
観光客になりすました犯人が、路上や電車内で質問をしてきます。そして、注意を引いている隙に共犯者が財布やカバンを抜き取る手口です。
☆一言アドバイス☆
貴重品の入っているカバンに常に注意を払いましょう。カバンのファスナー部分に手を置き、開けられないようにすることが重要です。リュックサックの外ポケットには携帯電話などの貴重品を入れないようにしましょう。
●洋服掛け犯
電車のボックス席に予め掛かっている他人のコートの上に自分のコートを掛け、その後、自分のコートを取るふりをし、他人のポケット等から金目の物を盗む手口です。
●ジャケット犯
犯人がレストランに入りターゲットと背中合わせに席を取り、ジャケットを背もたれに掛けます。そして、自分のジャケットに手をやるように見せかけて、対象者の背もたれに掛けてあるカバンや貴重品を盗む手口です。
☆一言アドバイス☆
電車内でコート掛けにジャケット類を掛ける場合には、貴重品をポケットに入れたままにしないようにしましょう。レストランやカフェ内では、椅子の背もたれにカバンを掛けたり、椅子の上カバンを置かないようにしましょう。
●窓ガラスノック犯
停車中の電車に犯人が乗り込み、車内を歩き回り対象を探します。その際、共犯者も同様に移動し、車内の犯人が格好の対象を発見すると共犯者が外から対象者が座っている窓ガラスをノックします。対象者がそちらに気をとられている隙に犯人が対象者の荷物を盗んで降りる手口です。
●コインばらまき犯
電車の車内において、わざとターゲットの周辺でコインをばらまき、対象者が拾うのを手伝っている隙に抜き取り係がカバン等を盗む手口です。
☆一言アドバイス☆
電車やトラム内では、貴重品の入ったカバンや荷物は、手を掛けておくなどして常に視界に入れておくことが大切です。見知らぬ人に話しかけられたら、疑ってかかり安易には対応しないようにしましょう。
●ホテルでの置き引き
ホテルの受付、ロビー、レストランや朝食会場などで、テーブルや足下に置いた貴重品やカバンを盗む手口です。
☆一言アドバイス☆
ホテル内でも窃盗等の犯罪は発生しています。カバン、バッグなど所持品から目を離さず、また所持品を自分の目の届かないところに無造作に置かないようにしましょう。
スリ・置き引き対策
特に気をつけるべき点は以下のとおりです。
➢ 所持品や手荷物は身体の前で抱え、決して目を離さない。また、財布や旅券など貴重品は上着の内ポケットに入れるなど肌身離さず携行する。
➢ 多額の現金・貴重品を持ち歩かない(現金は分散して持つ)。また財布などをむやみに取り出さない、他人に見せない。
➢ 見知らぬ人から話しかけられても、むやみに信用しない(まずは疑ってかかる)。
➢ 身体を押されたり、触られたりした場合など、常にバッグなどの手荷物をチェックする(ファスナーが開けられていないか)。
➢ 路上(屋外)や主要駅、地下鉄駅構内の ATM は極力利用しない(銀行など店舗内のATM を利用)。
➢ ATM で現金を引き出す際、また引き出した後は、周囲を十分警戒する(周囲を見渡して不審な人物が自分を見ていないか確認)。
(イ)詐欺
空港や駅などで旅行者を狙った詐欺が発生しているほか、携帯電話やインターネットを使用した詐欺被害が多数報告されています。主な手口は以下の通りです。
●空港や駅でのクレジットカード詐欺
空港で外国人が、あたかも知人に日本人がいるかのように「タナカ」という名前を出しつつ、「フライトがキャンセルとなったため航空会社に電話したいが、クレジットカードを持っていないので20ユーロと引き替えにクレジットカードを使用させてほしい」と依頼してきたので、クレジットカードを渡したところ、同種のカードにすり替えられており、後日、不正使用されていたというケースが発生しています。
●偽警察からの詐欺電話
警察またはその他の当局のメンバーであると名乗る者から携帯電話を介して電話がかかってきて、英語で「あなたの身分証明書、スイスID口座、銀行口座に不正がある」と主張し、銀行口座やID番号などの個人情報を聞き出そうとするケースが報告されています。
●SMSやEmailによるフィッシング詐欺
税関・国境警備局やスイスポストを名乗る詐欺師が支払いを要求する、いわゆる「フィッシング」メッセージを受け取る個人や企業が増えています。このようなメッセージは、税関・国境警備局やスイスポストのロゴを無断で使用し、巧みに模倣文書を作成し、受信者に荷物を受け取るために送金する必要があると信じ込ませます。税関・国境警備局から電子メールやテキスト・メッセージによる支払請求の送信が行われることはありませんのでご注意ください。
詐欺対策
➢ 不審な電話があったらすぐに通話を切る。
➢ SMSや電子メールにあるリンク先をたどらない。
➢ 不審なSMSや電子メールに対応せず、すぐに削除する。
➢ 口座情報、クレジットカード情報、ID番号など個人情報を第三者に教えない。
➢ 口座情報、クレジットカード情報を教えてしまった場合、すぐに銀行及びクレジットカード会社に連絡し、カードを停止してもらう。
➢ クレジットカード類は他人に渡さない。見ず知らずの人に支援を求められても容易に信用せず、警察に相談するよう返答する。
ウ 被害に遭ってしまったら
(ア)警察及び大使館や総領事館への通報まずは警察(117番)に連絡してください。ホテルやレストランでは従業員に警察への通報を依頼することも可能です。一人で対処しようとせず、周りの人へ助けを求めてください。また、後日、被害品が発見された場合に在外公館に連絡がある場合もあるので、最寄りの在外公館にも連絡をしておくことが賢明です。
(イ)クレジットカードの利用停止手続き
クレジットカードの盗難や紛失にあたっては、早急に利用停止の手続きを取ってく ださい。連絡先は以下のとおりです。
➢ KDDI ジャパンダイレクト(スイスアクセス番号):0800-55-0081(コレクトコール可)
➢ 本手引き(7)緊急時の連絡先「クレジットカード会社緊急連絡先」をご参照ください。
(ウ)盗難・紛失証明書の入手
盗難被害にあたっては、盗難に遭った日時や場所、被害品目等の詳細を警察に届け出て、警察から盗難証明書(Bescheinigung Diebstahl)を発行してもらう必要があります。なお、パスポートの再発給(または「帰国のための渡航書」発給)や保険請求には、 警察からの盗難・紛失証明書が必要となります。
警察への届出はオンラインでも可能なものもあります(緊急時は117番に連絡し てください。)。
➢ スイスePoliceのウェブサイト:https://www.suisse-epolice.ch/home
(エ)帰国のための渡航書の発給
必要書類は以下のとおりです。
➢ 紛失届出書及び発給申請書(当館にあります。来館時にご記入ください)
➢ 写真2葉(縦 4.5cm×横 3.5cm)(6ヶ月以内に撮影されたもの)
➢ 警察の盗難・紛失証明書(Bescheinigung Diebstahl/Verlust)
➢ 戸籍謄本(6か月以内に発行されたもの。戸籍抄本では受け付けできません。)、日本国籍を有することを証明する文書等(本籍地が記載された住民票等、1通(いずれもコピー可。)または戸籍電子証明書提供用識別符号
➢ 航空券予約確認書
紛失または盗難として現地警察に届け出た日本国パスポートは、その後無事見つかったとしても紛失または盗難として現地警察に届け出た日本国パスポートは、その後無事見つかったとしてもヨーロッパでは使用できません。また大使館等に紛失一般旅券等届出書を提出された後、紛失された旅券が見つかりましてもその旅券は無効であり使用できません。
現在、旅券は申請からお渡しまで通常約2~4週間ほどかかります。
第三国にお住まいで、スイスから居住国に戻られる場合は、当館にご連絡ください。
エ スイス社会への融合
スイスに滞在するうえで、スイスの法律・制度・習慣等に従うことは重要です。そこで、普段から隣人・コミュニティ・在留邦人等と付き合い、良好な関係を築き上げ様々な人や組織との間でネットワークを作ることをお勧めします。ネットワークができれば、いざというときに助けが得られ、様々な情報が入ってきます。現地コミュニティ・隣人等の「口コミ」情報には極めて重要な要素が含まれていることがあります。このために、スイス各地に点在する日本人会、同好会に加入するのも一案です。スイスに慣れ親しんだ方が多数在籍しておられますので、その方々の助言を受けながらスイスに馴染んでいくことも一つの手段です。(4) 交通事情と事故対策
ア 交通事情
(ア)制限速度は、市街地は50km/h(一部住宅地等は30km/h)、郊外一般道路は80km/h、高速道路は120km/h となっていますが、特別に速度が制限されている場所があるので常に速度標識に注意して走行する必要があります。(イ)優先標識が無い交差点においては、「右側からの車両が優先」されます。右側から車が進入してくる場合、直進車は停止しなければなりません。但し、「優先道路標識」がある場合や右側車線の道路上に「前方優先」の標記がある場合は異なります。なお、「優先道路標識」のないロータリーでは左側からの車両に優先権があります。
参考:TCS(TOURING CLUB SUISSE:日本のJAFに相当)
交通法規(独語) 交通法規(仏語)
(ウ)身長150cmに満たない12歳未満の子供はチャイルドシートが必要です。
(エ)昼間でもヘッドライトを点灯しなければなりません。
(オ)車内に安全ベスト(人数分)を常備しましょう。
(カ)事故発生時に対処するための事故処理カードを準備しましょう。(保険加入時に保険会社から配布される事が多いと伺っております。)
(キ)冬季は山岳部で積雪し、平野部においても降雪が度々見られるので、冬季用タイヤへの交換が必要です。冬季用タイヤでない場合、保険が適用にならない場合がありますので注意が必要です。
(ク)当地では街中の至る所に速度違反や信号無視を取り締まる無人カメラが設置されており、違反をすると後日罰金の支払請求書が送られてきます。また駐車違反の場合、その場で罰金の支払請求書を当該違反車両に貼られるか、又はレッカー移動されることもあります。
悪質な違反の際には、収入に応じた高額の罰金を課されることがあります。いずれにせよ、安全運転に努め、交通規則を遵守してください。
イ 事故を起こしてしまったら(基本的に日本で事故を起こした時と同じです。)
●停止表示機(三角板)を設置し、非常点滅等を点滅させ停車する。●負傷者を救助し、救急車及び警察へ連絡する。
●事故証明を取得するとともに、車の保険会社に連絡する。
(5) テロ対策
スイスにおいては、テロ組織、反政府組織や国際的なテロ組織の関連組織による活発な活動は確認されていません。しかしながら、2023年12月にフランスパリのエッフェル塔の近くで刃物とハンマーを持った男が通行人を襲撃する事件の発生や、2024年8月にドイツのゾーリンゲンで市創設650周年祭りの最中に男が路上で多数をナイフで襲撃する殺傷事件が発生するなど、欧米では、近年、警備や監視が手薄で一般市民が多く集まる場所(ソフトターゲット)を標的としたテロが頻発しています。このような情勢を十分に認識し、海外安全情報、報道等により最新の治安、テロ情勢等の関連情報の入手に努め、日頃から高い危機管理意識を持つよう心がけてください。ア 基本的な対策
➢ テロの標的となりやすい場所を訪れる際には、周囲の状況に注意を払い、不審な動きをしている人物や状況を察知したら、速やかにその場を離れてください。テロの標的となりやすい場所として考えられるのは、公共施設や観光施設、大勢の人が集まる場所、賑やかな市場、ショッピングセンター、公共交通機関(バス、鉄道、航空、海上)、スポーツイベント、文化イベント、有名な国際ホテル、人気のレストランなどです。
➢ 報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努めてください。新聞、テレビ、ラジオなど以外にも、FacebookやXなどのSNSからも有益な情報が収集できます。
➢ 家族全員の日程を把握しておくよう心掛け、いざというときの連絡手段についても確認しておくことが有効です。
イ テロに遭遇したら
テロに遭遇したら、「逃げる」「隠れる」「警告する」ことが重要です。
(ア)「逃げる」
➢ 危険な場所から離れる経路を探す。
➢ 逃走中に姿をさらさないようにし、身を潜め、目立たないように行動する。
➢ 周囲の人に危険地帯に入らないように警告する。
➢ 自分の安全確保が第一ですが、可能なら周囲の人を助けてあげましょう。
(イ)「隠れる」
➢ 建物内でテロが発生した場合、犯人が入ってこないようドアを施錠し家具などでバリケードを築く。
➢ 照明を消し、携帯電話の音声とバイブレーションのスイッチを切る。
➢ 建物のドアや窓から離れ、床に低い姿勢で留まる。
➢ 建物内の安全な壁の後ろに隠れる。
(ウ)「警告する」
➢ 警察(117)に通報する。
➢ 警察官のもとに避難する場合、走らず落ち着いて移動する。
➢ 警察官に出くわしたら、両手を上げて空の手のひらを見せる。
安全な場所に移動することが出来た後、自らの安否情報、把握出来た安否情報、その他現場の状況などを緊急連絡先(家族)や管轄の在外公館へ共有してください。
(6) 自然災害(防災)
ア 概要当地においては突発的に自然災害事案が発生する可能性もあるため、滞在中は、当地行政機関や報道などによる情報発信に日頃から関心を持って生活してください。なお、大使館は自然災害情報を入手した場合、在留邦人の皆様へ情報提供いたします。皆様の安全安心のため、緊急時に連絡できるよう在留届の提出またはたびレジの登録に是非ご協力願います。
また、災害発生時には在留届の情報に基づき安否確認を行いますので、在留届の内容を常に最新の内容にして頂きますようお願いいたします。甚大な自然災害の際には、通信トラブルが発生する可能性があります。その際、大使館から皆様への連絡に努めますが、ご家族に対して無事を伝えるとともに、可能な限り大使館に連絡してください。
なお、連邦市民保護局は、スイスによる情報収集及びアプリのダウンロードをスイス国内居住者に呼び掛けています。
アラートスイス:https://www.alert.swiss/
イ 緊急事態用物資等の整備緊急事態が発生した場合には、食料、飲料水、医薬品、燃料等の入手が困難となることが予想されますので、普段より非常用物資を備蓄しておくよう心がけて下さい。備えの一例は以下のとおりです。なお、備蓄物資の中には長期保存に適さないものもありますので、随時使用期限を確認しておいてください。
(ア)非常用食料(7~10日分程度)
(イ)飲料水(7~10日分程度)、飲料水用容器
(ウ)医薬品
(エ)燃料、懐中電灯、ろうそく、マッチ、乾電池、ケロシンランプ
(オ)携帯型ラジオ
(カ)衣類、寝具(毛布等)
(キ)食器、炊飯道具
(ク)携帯電話(予備バッテリーを含む)
(ケ)旅券(有効期限が6ヶ月以上残っているか)
(コ)入国査証(必要に応じて)
(タ)海外旅行保険
(チ)カード類(クレジットカードを含む)
(ツ)現金
ウ 避難方法
(ア)自宅待機:特定区域で自然災害が発生し、自宅周辺に直ちに影響が及ぶ可能性が低い場合は、自宅に待機して連絡手段を確保しつつ情報収集に努めてください。
(イ)一時退避:自然災害や火事等で居住地周辺に危険が迫り、自宅内に残留すると被害が及ぶ可能性が高くなった場合は、知人宅やホテル等に避難し、日本大使館に連絡先を伝えるとともに情報収集に努めてください。
なお、スイス国内には避難シェルターを整備している自治体が多くありますが、場所等の案内は非常事態が発生した際に自治体からインターネットやラジオ等で情報を発信します。緊急時のサイレンがなったら、スイス公共放送局(SRG SSR)または地元のラジオやニュースサイトで情報収取に心掛けてください。
スイス公共放送局 :
SRF(ドイツ語): https://www.srgssr.ch/en/our-offering#srf
RTS(フランス語): https://www.srgssr.ch/en/our-offering#rts
情報収集元:
自然災害ポータル:https://www.naturgefahren.ch/home.html?tab=actualdanger
メテオスイス: https://www.meteoswiss.admin.ch/#tab=forecast-map
エ 山岳事故に関する注意事項
スイス国内の山では、クレバス(氷河の裂け目)への滑落事故、登山中の死亡・負傷事故や行方不明が毎年発生しています。グリンデルワルト、ツェルマット、サンモリッツ、マッターホルン、モンブラン山系(仏領を含む)等において本格的な登山をする場合は、事前に地元ガイドのアドバイスを十分に聞き、装備を怠りなく、無理をしないよう心掛けてください。邦人ツアー客の死亡事故も毎年のように発生しています。また、短時間の簡易なハイキングであっても、旅行の疲労や急な気圧の変化等により、ハイキング中または下山後、脳梗塞等により緊急入院するケースも散見されるため、健康管理には十分注意してください。
また、スイスは全般的に海抜が高く、さらに登山電車やケーブルカー等の発達で比較的簡単に2,000メートルを超える高い山に登られますが、急な気圧の低下により体調を崩す場合がありますので、特に心臓の弱い方、体調の悪い方、お年寄り、小さなお子様は絶対に無理をしないように注意してください。
外務省海外安全ホームページの「重要なお知らせ」(海外における登山、トレッキングに関する注意:https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_tozan.html)もあわせてご参照ください。
(7) 緊急時の連絡先
【現地緊急対応機関】| 警察 | 117 | ||
| 主な警察署 | |||
| Polizeiwache Waisenhaus |
ベルン 旧市街内 |
住所: Waisenhausplatz 32, 3011 Bern 電話: +41 (0)31 638 81 11 |
|
| Polizeiwache Bahnhof |
ベルン駅 地上階 |
住所: Bahnhofplatz 10, 3011 Bern 電話: +41 (0)31 638 82 30 |
|
| Polizeiposten Flughafen |
チューリッヒ 空港内 |
住所: 8058 Zürich-Flughafen 電話: +41 (0)58 648 50 50 |
|
| Polizeiposten Hauptbahnhof |
チューリッヒ 中央駅内 |
住所: Museumstrasse 1, 8021 Zürich 電話: +41 (0)58 648 68 10 |
|
| Polizeiposten Rathaus |
チューリッヒ 市庁舎内 |
住所: Limmatquai 61, 8001 Zürich 電話: +41 (0) 58 648 68 20 |
|
| 消防 | 118 | ||
| 救急 | 144 | ||
| スイス鉄道交通警察 | 0800 117 117 | ||
| スイス毒物情報センター Schweizerisches Toxikologisches Informationzentrum |
145 住所:Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich 電話:+41 44 251 66 66 +41 (0) 44 251 51 51(国外からの緊急連絡) E-mail: info@toxinfo.ch HP:https://toxinfo.ch/startseite_en |
||
| 航空救助隊 Rega |
電話:1414 (スイス国内のみ) :(+41 333 333 333(国外からの緊急連絡)) HP:https://www.rega.ch/en/ |
||
【医療機関等】
| 緊急医師紹介サービス | ベルン市 電話:0900 57 67 47 チューリッヒ市 電話:0800 33 66 55 バーゼル・シュタッド準州 電話:+41 (0)61 261 15 15 |
| 大学病院・州立病院 | ベルン・インゼル病院 電話:+41 (0)31 632 2111 チューリッヒ大学病院 電話:+41 (0)44 255 1111 バーゼル大学病院 電話:+41 (0)61 261 1515 |
| スイス連邦保健庁Federal Office of Public Health FOPH | 住所: Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Bern 電話: +41 (0)58 462 21 11 HP: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html |
【登山・観光情報提供施設】
| メード・イン・ベルン *ベルン観光局 |
電話番号:+41 (0)31 300 3300 住所:Thunstrasse 8, 3005 Bern ホームページ(英語) https://www.madeinbern.com/en/home-en |
| ツェルマット *ツェルマット観光局 |
電話番号:+41 (0)27 966 81 00 住所:Bahnhofplatz 5, 3920 Zermatt ホームページ(英語) https://zermatt.swiss/en |
| エンガディン *エンガディン(サンモリッツ) 観光案内所 |
電話番号:+41 (0)81 830 0001 住所:Via Maistra 1, 7500 St. Moritz ホームページ(英語) https://www.engadin.ch/en |
| シャモニー(モン・ブラン) *山岳情報センター |
電話番号:+33 (0)4 5053 22 08 住所:Maison de la Montagne, 190 Pl de l'Eglise 74400 Chamonix Mont-Blanc ホームページ(英語) https://www.chamoniarde.com/en |
【クレジットカード会社緊急連絡先】
| VISA | 電話: 0800-89-4732 1 303 967 1096(コレクトコール) HP: http://www.visa.co.jp/personal/benefits/lostyourcard.shtml |
| 三井住友VISAカード | 電話: +81 (03) 6847 02 98 HP:https://www.smbc-card.com/mem/goriyo/lost.jsp |
| JCB | 電話: 0800 55 6056 HP:https://www.jcb.co.jp/support/lost-and-stolen.html |
| MASTER | 電話: 0800 897 092 HP: https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/consumers/get-support/issuer-contact-information.html |
| AMERICAN EXPRESS |
電話: 0800 55 47 03 0800 55 47 02(ゴールドカード) HP: https://www.americanexpress.com/jp/jp-home/sitehelp/lost_stolen.html |
| DINERS | 電話: +81 (0)3 6852 0931 HP:https://www.diners.co.jp/ja/contact.html |
| MUFGカード | 電話: 00 800 0249 1468 HP: http://www.cr.mufg.jp/mufgcard/contact/lost_ab/index.html |
| DCカード | 電話: +81(0)3 3770 1818 HP: http://www.cr.mufg.jp/dc/contact/lost_ab/index.html |
| NICOSカード | 電話: 00-800-99-860860 HP: http://www.cr.mufg.jp/nicos/contact/lost_ab/index.html |
| UCカード | 電話: +81(0)3-5996-9130 HP:https://www2.uccard.co.jp/cs/sos/index.html |
(8)緊急時の言葉(ドイツ語、フランス語)
| 助けて! | 【独】 | Hilfe! (ヒルフェ) |
| 【仏】 | Au Secours! (オ スクール) |
|
| 警察を呼んで下さい! | 【独】 | Rufen Sie bitte die Polizei an! (ルーフェン ジー ビッテ ディー ポリツァイ アン) |
| 【仏】 | Appelez la police ! (アプレ ラ ポリス) |
|
| 警察署はどこですか? | 【独】 | Wo ist die Polizeistation? (ヴォー イシュトゥ ディー ポリツァイスタチオン) |
| 【仏】 | Où se trouve le poste de police? (ウス トゥルーヴ ル ポスト ドゥ ポリス) |
|
| 泥棒です! | 【独】 | Dieb! (ディーブ) |
| 【仏】 | Voleur! (ヴォルール) |
|
| 彼(彼女)を捕まえてください! | 【独】 | Schnappt ihn (sie)! (シュナップトゥ イン(ジー)) |
| 【仏】 | Attrapez-le(la) ! (アトラペ ル(ラ)) |
|
| バッグ(財布/パスポート)を盗まれました。 | 【独】 | Meine Tasche (Portemonnaie/Reisepass) wurde gestohlen. (マイネタッシェ(ポートモネ/ライゼパス) ヴーデゲシュトーレン |
| 【仏】 | Mon sac (porte-monnaie/passeport) a été volé. (モンサック(ポルトモネ/パスポール)ア エテ ヴォレ) |
|
| バッグ(財布/パスポート)を失くしました。 | 【独】 | Ich habe meine Tasche (Portemonnaie/Reisepass) verloren. (イッヒハーベマイネタッシェ(ポートモネ/ライゼパス)フェローレン) |
| 【仏】 | J'ai perdu mon sac (portefeuille/passeport). (ジェ ペルデュ モンサック(ポルトフーユ/パスポ)) |
|
| 紛失証明書(盗難)が必要です | 【独】 | Ich brauche eine Verlust(Diebstahl)anzeige. (イッヒ ブラウヘ アイネ フェアルスト (ディエブシュタール)アンツァイゲ) |
| 【仏】 | J'ai besoin d'une attestation de perte (vol). (ジェ ブゾワン ドュヌ アテスタシォン ドゥ ペルトゥ(ヴォル)) |
|
| 火事です! | 【独】 | Feuer! (フォイヤー) |
| 【仏】 | Au feu! (オ フー) |
|
| 消防車を呼んでください! | 【独】 | Rufen Sie die Feuerwehr! (ルーフェン ジー ディー フォイヤーヴェー) |
| 【仏】 | Appelez les pompiers! (アプレ レ ポンピエ) |
|
| 危ない! | 【独】 | Achtung! (アハトゥング) |
| 【仏】 | Attention! (アトンシォン) |
|
| 救急車を呼んで下さい! | 【独】 | Rufen Sie eine Ambulanz! (ルーフェン ジー アイネ アンビュランツ) |
| 【仏】 | Appelez une ambulance! (アプレ ユ ナンビュランス) |
|
| 気分が悪いです。 | 【独】 | Ich fühle mich nicht wohl. (イッヒ フューレ ミッヒ ニヒト ウォール) |
| 【仏】 | Je ne me sens pas bien. (ジュヌム ソンパ ビアン) |
|
| 英語を話せますか? | 【独】 | Sprechen Sie Englisch? (シュプレヒェンジー エングリッシュ?) |
| 【仏】 | Parlez-vous anglais? (パルレ ヴー オングレ?) |
|
| 道に迷いました | 【独】 | Ich habe mich verlaufen. (イッヒ ハーベ ミッヒ フェアラウフェン) |
| 【仏】 | Je suis perdu. (ジュ シュイ ペルデュ) |
3 在留邦人用緊急事態対処マニュアル
(1) 平素の準備と心構え
ア 在留届の提出
情報提供、安否確認、避難に関するお知らせ等は在留届に基づいて行います。 当地で3か月以上滞在される方は必ず在留届を提出いただくとともに、 連絡先を含めその内容を常に最新の状態にしていただくようお願いいたします。転居や帰国の際も必ず変更の届出を行って下さい。
(変更の届出は、電話、メール、郵便、またはオンライン在留届の場合はORRネットからも受け付けています。)
在留届の提出(ORRネット)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
イ 連絡体制の整備
大使館からの緊急連絡は、在留届に基づいて行いますが、在留邦人の皆様が組織しているグループや団体(各地域の日本人会など)で独自の連絡網を作成しておられましたら、大使館にご連絡ください。これらの連絡網を緊急事態の際の連絡に活用したいと考えております。
ウ 退避場所
緊急事態はいつ起こらないとも限りません。そのような場合に備えて家族間や企業内などでの緊急連絡方法や退避場所、集合場所を日頃から決めておき、適時確認を行ってください。また、各自の日常の所在も家族や同僚などに知らせておくことが大切です。
エ 携行品及び非常用物資の準備
旅券や身分証明書のほか、最低必要な現金は直ちに持ち出せるように予めまとめておきます。また、非常用食料品、医薬品などを家族構成に合わせ、日頃から準備しておくことが大切です。
携行品
(1) 身分証明書類(旅券、滞在許可証、運転免許証など)
(2) 現金、クレジットカード、キャッシュカード
(3) 車や家の鍵
(4) 携帯電話、充電器
(5) 防寒着、雨衣、帽子及び手袋
(6) 時計、筆記具、地図
(7) ある程度の強度及び保温性のある靴
(8) その他ご自身の生活に欠かせないもの
非常用物資
3日分程度準備しておくことをお勧めします。食糧について、特に避難初期はそのままで食べることのできるものが便利です。
(1) 食糧
(2) 水
(3) 医薬品(救急セット、常備薬、持病薬)
(4) 衣類(下着を含む)
(5) トイレットペーパー、タオル、ウェットティッシュ
(6) その他ご自身の生活に欠かせないもの
次項ALERT SWISSのサイト掲載の緊急時の携行品・非常用物資の各言語(独・仏・伊・英)リストをご参照ください。独・仏・伊語版には平易な説明版のリストもあります。
(https://www.alert.swiss/en/precaution/emergency-plan.html)(英語)
オ ALERT SWISS
連邦及び州政府の共同事業による危機管理用サイトでは、平時の情報収集から緊急時の対応まで掲載されていますので、ご利用ください。
(https://www.alert.swiss/en/home.html)(英語)
また、スマートフォン用アプリでは、スイスの26州及びリヒテンシュタインの中から情報を得たい場所(一部の州又は全地域、更に位置情報による現在地)と、情報内容(事故のような一般情報から災害等の注意報、警報まで)を自由に選択することができます。
(2) 緊急時の行動
ア 基本的心構え
平静を保ち、流言等に惑わされ、群集心理に巻き込まれることのないように注意してください。
イ 情報の把握
緊急事態発生の際には、連邦政府公式発表、当地報道、ラジオ、インターネットの他、日本の外務省からも情報を得られます。緊急時には誤った情報や噂が流れやすくなりますので、落ち着いて、正確な情報の収集に心掛けてください。
外務省領事局海外邦人安全課 03-3580-3311 (内線)5140
外務省海外安全相談センター 03-3580-3311 (内線)2902
外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/
ウ 大使館との連絡等
ご自身やご家族又は他の在留邦人の方の生命・身体・財産に危害が及んだとき、又はそのおそれがある場合には、迅速かつ具体的にその状況を大使館にお知らせください。
また、緊急事態発生の際には、お互いに助け合って対応に当たることが必要となります。場合によっては、大使館から在留邦人の皆様に種々のお願いをすることもあるかと思いますので、その際にはご協力をよろしくお願いいたします。
大使館は邦人の方々のさらに詳しい状況を把握するために、領事メールやインターネットを利用したアンケートを通じて安否確認を行うこともあります(インターネットを利用したアンケート方式の安否確認の例は、次のとおりです)。
いずれにしましても、緊急事態が発生した際に安否確認を行うためには、メールアドレスや携帯番号が必要になりますので、「在留届」又は「たびレジ」への登録をお願いします。
■インターネットを利用したアンケート方式による安否確認
ア.「在留届」または「たびレジ」に登録されたメールアドレスに、大使館のメールアドレスから安否確認のメールが送付されます。
イ.アンケートに回答を入力後、返信して完了です。なお、回答内容により、電話、メール等を通じ、大使館から回答者に対して連絡が行われることがあります。